 HOME HOME
 井上醸造の味噌造り 井上醸造の味噌造り
第一章 こうじ造りについて
第二章 大豆について
第三章 仕込みについて
 商品のご案内 商品のご案内
 新着情報 新着情報
 お味噌汁お試しセット お味噌汁お試しセット
 冬の味覚 しょうゆ豆 冬の味覚 しょうゆ豆
 冬季限定 つましな 冬季限定 つましな
 春限定 仕込みそ 春限定 仕込みそ
 ご購入について ご購入について
 FAX注文用紙 FAX注文用紙
 Publicity Publicity
 GALLERY GALLERY
 季節の便り(春夏編) 季節の便り(春夏編)
 季節の便り(秋冬編) 季節の便り(秋冬編)
 MAP ご来店のお客様へ MAP ご来店のお客様へ
 サイトマップ サイトマップ
お買い物カート
特定商取引法に基づく表示
プライバシーポリシー
 
 

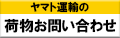
長野県長野市妻科167
TEL:026-232-5427
FAX:026-232-5437
http://www.inouejyozo.jp
 :miso@inouejyozo.jp :miso@inouejyozo.jp |
第二章 みその個性を決める大豆の蒸煮(じょうしゃ)
〜醸造技術の原点 無圧蒸し〜

おいしい味噌を造るためには良質の大豆の確保が必要です。井上醸造は長野県産を中心に全量国内産の大粒白目大豆を使用しています。
国産使用比率100%を謳うことの出来る数少ない味噌メーカーです。
たんぱく質が多く脂質が少ない国産大豆は甘味旨味があるばかりではなく、保水率がよく、キメの細かさに特徴があり、私達が理想とする味噌を造るために欠かせない原料です。
味噌造りの極意を表す格言「一こうじ、二炊き、三仕込み」の“炊き”とは、洗った大豆を水に浸す浸漬(しんせき)をへて大豆を蒸煮(じょうしゃ)する原料処理の工程を指します。
特に大豆をどう蒸したり煮たりするかで、味噌の出来栄えが左右されるため、「こうじ造り」とともに味噌造りにとってはとても大切な工程です。
大豆蒸煮の目的は、「熱を加えることで大豆を軟化させて、こうじの酵素作用を受けやすくするため」ですが、それに加えて井上醸造では“大豆の旨味をいかに引き出すか”に力点を置いています。
8袋(240キロ)前後の大豆を、洗穀機で充分な水量で磨くように洗い、水を張った浸漬桶の中に投入していきます。水温、気温、大豆の産地、作柄により吸水の条件は異なるので、浸漬には微妙な時間調整が必要になります。こうして大豆の芯まで完全に吸水させて仕込み当日を迎えます。
現在、ほとんどの味噌メーカーでは、圧力釜(加圧缶)で高圧をかけ短時間に蒸煮します。色が明るく仕上がるものの、この方法では、せっかくの旨味と養分が煮汁に逃げ出してしまいます。その上、全国で生産される味噌の約95%が輸入大豆を原料につくられていることも、「味噌が個性を無くしてきた」と言われる原因の一つではないでしょうか。
井上醸造では、「少しでもおいしい味噌を追求するため=大豆の旨味を引き出すため」昔ながらの“無圧蒸し”にこだわり続けています。
 朝5時、浸漬桶の水を払い(水切り)、甑(こしき)に蒸気を入れ、蒸しむらの出ないよう蒸気の抜けた(上がった)ところに、手作業でザル1杯ずつ浸漬大豆を張り込んでいきます。 朝5時、浸漬桶の水を払い(水切り)、甑(こしき)に蒸気を入れ、蒸しむらの出ないよう蒸気の抜けた(上がった)ところに、手作業でザル1杯ずつ浸漬大豆を張り込んでいきます。
完全吸水した大豆は洗う前の約2.2倍に膨らむので、重量は約500キロにもなり、その作業は決して楽ではありません。そして完全に蒸気が抜けてから重石をして、時間をかけてゆっくりと蒸しあげていきます。

早朝から約半日の作業をかけて蒸しあげた大豆は、親指と小指(人差し指じゃダメなんです)でつまむと軽く潰れるほどの軟らかさとなり、芳ばしい香りがします。
ほんのりとアメ色を呈し、甘味と旨味が濃厚で「このまま食べてもおいしい!」これが、井上醸造の“蒸し”の技術です。
 私たちは、大豆畑を見させていただくたびに「大変なご苦労を経て収穫に至るのだ」と頭の下がる思いがします。 私たちは、大豆畑を見させていただくたびに「大変なご苦労を経て収穫に至るのだ」と頭の下がる思いがします。
井上醸造では、生産者の方々が大事に育て上げたその大豆の一粒一粒を、時間をかけて丁寧に処理していくことが、やがておいしい味噌となって食卓へと繋がっていくものだと信じています。
第三章 仕込み 〜季節にそったみそ造り〜 はこちら
|







 朝5時、浸漬桶の水を払い(水切り)、甑(こしき)に蒸気を入れ、蒸しむらの出ないよう蒸気の抜けた(上がった)ところに、手作業でザル1杯ずつ浸漬大豆を張り込んでいきます。
朝5時、浸漬桶の水を払い(水切り)、甑(こしき)に蒸気を入れ、蒸しむらの出ないよう蒸気の抜けた(上がった)ところに、手作業でザル1杯ずつ浸漬大豆を張り込んでいきます。
 私たちは、大豆畑を見させていただくたびに「大変なご苦労を経て収穫に至るのだ」と頭の下がる思いがします。
私たちは、大豆畑を見させていただくたびに「大変なご苦労を経て収穫に至るのだ」と頭の下がる思いがします。